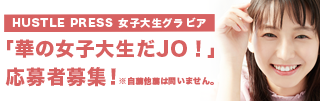大人を泣かす一心不乱の青春 ~映画「青空エール」随想~
「頑張れ」と言うなら自分も頑張る
土屋太鳳のひたむきさが胸を打つ
「高校生活は3年間かけてやる合コンですよね」。ある女性タレントから取材中に出た言葉だが、なるほどなと思った。男女が集まり、常に恋愛しやすい環境。個人的には、その“合コン”のなかで、同じクラスの吹奏楽部の女子が気になっていた時期があった。何か金管楽器を吹いていたと記憶している。
大人が青春映画を観る楽しみのひとつは、自らの“あの頃”が(少し美化されて)蘇ること。まして土屋太鳳が吹奏楽部員を演じる恋愛モノとなれば、自分にうってつけ……と観に行ったのが「青空エール」だった。
しかし、まず蘇ったのは「おのれ野球部!」という妬み。土屋の役の恋の相手は野球部員だが、昔は今以上に野球部は特別だった。部活のひとつなのに、新聞の地方版に県大会の全出場校の選手名簿が載り、“甲子園を目指して”と1回戦から詳細に報道されて。「俺たちの地区予選もやってるのにな……」とは、野球部以外のすべての運動部員が一度は思ったはず。
自分のいた高校の野球部は毎年せいぜい3回戦レベル。それでも校内では花形扱い。「青空エール」の吹奏楽部は南北海道大会の決勝だけ応援に入っていたが、うちの高校では初戦から部の“有志”が演奏するのが習わしだったらしい。「で、その有志に入るの?」と片想いしていた金管の彼女に聞いたら、「うん。私は応援するよ」と。おのれ野球部……などと書いていると、ちっちゃい昔の自分に恥じ入るが、まあ羨ましかったのだ。
「青空エール」で土屋太鳳が演じた小野つばさは、テレビで観た甲子園で応援するブラスバンドに憧れ、吹奏楽の名門・白翔高校に入学する。そして、同じ試合を観て甲子園を目指した同級生の山田大介(竹内涼真)と約束を交わす。「俺、絶対に甲子園に行くから、そのときスタンドで応援してくれる?」と。
それから高3の夏までが描かれるこの映画。三木孝浩監督は大人のために作ったのではないか? とさえ思った。つばさたちはスマホでLINEしたりしているが、「タッチ」を思わす“約束”から空気が昭和っぽいというか、自分たち中年世代の“あの頃”を感じさせて。
土屋と竹内のコンビも美女美男ながら、今ドキな顔立ちではない。何より劇中の2人の関係性。1年の夏の地区予選の決勝で野球部が敗れたあと、つばさは大介に「好きって言ったら困る?」と告白して「ごめん、つき合えない」と断られる。決勝で自分のエラーから甲子園行きを逃した大介は、野球に専念しようとしていて。
フラれたつばさのほうは大介を応援する気持ちを持ち続け、吹奏楽部でコンクールのメンバーに入るためにもトランペットに打ち込む。2人は“同じ場所を目指す同志”として握手を交わしたりもする。握手とはまた品行方正な。
そんなの今ドキ、あるのだろうか? 野球は野球で頑張って、好きな女の子とつき合うのはいいんじゃないの? 大介も密かに神社で絵馬に「小野を甲子園に連れていく!」と書いていたりするんだし(絵馬というのも昭和っぽい)。あるいは“3年かけてやる合コン”としては、1年の夏でフラれたならドンマイで次に行くところ。でも、そんなノリは皆無。こんなストイックな高校生たちなんて……と思って、ハッと気づいた。
いつも長文で誠実な土屋太鳳のブログで以前、進学する高校を決めたときの話が書かれていたことがあった。
「私は、高校は女子校に行こうと決めてました。 お仕事がちゃんと出来るようになるまでは修行中だから、お芝居の中の役としてしか恋愛しない、と決めてるんですが」
いたじゃん、そんな女子! スクリーンのなかの土屋太鳳その人。「修行中」か……。
「青空エール」では2人は恋人でなく、互いへの想いを胸に秘めながら相手が頑張っているのを近くで感じて、励みにし合う間柄になっていた。
「頑張ってるの見てたら、自分も一生懸命、応援したくなる。この言葉に出来ない気持ちも、音にはこめられるから」
つばさはそう言っていたが、音に気持ちがこめられるまでには、どれだけ練習が要るのだろう。人に「頑張れ」と言うなら、自分はそれ以上に頑張らなくてはいけない。自分以上に頑張ってる人からの「頑張れ」は本当の力になる。それが“エール”。共に名門の野球部と吹奏楽部という設定が最高に光る、古めかしくも美しい青春映画だった。
あの頃、名もない高校の部活でも、ただ勝ちたいと思っていた。バカみたいに諦めようとせずに。大人になって現実と折り合いをつけながら忘れていた気持ちが、1人で教室に残ってトラッペットを吹くつばさのひたむきさに呼び起こされ、胸が熱くなった。それは土屋太鳳自身の演技に対するひたむきさとも重なる。だからいつも、彼女の演じる役には心が波打つ。
それと吹奏楽部の演奏。あんな音が毎日、放課後の部活中の学校で聞こえていたっけ。つばさと大介と違い、好きだった女の子が自分を想って吹いてくれていたわけではないけれど、バテて水飲み場で倒れそうになりながら、その音に彼女の存在を感じていた。そんな夕暮れの記憶も「青空エール」でフラッシュバックした。忘れたくない音だと思った。
ライター・旅人 斉藤貴志